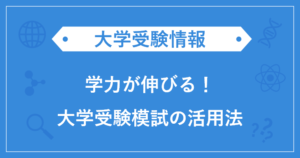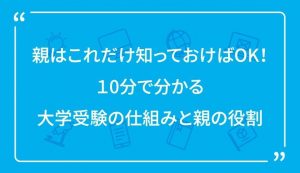【小論文の書き方】例文と一緒に詳しく解説!
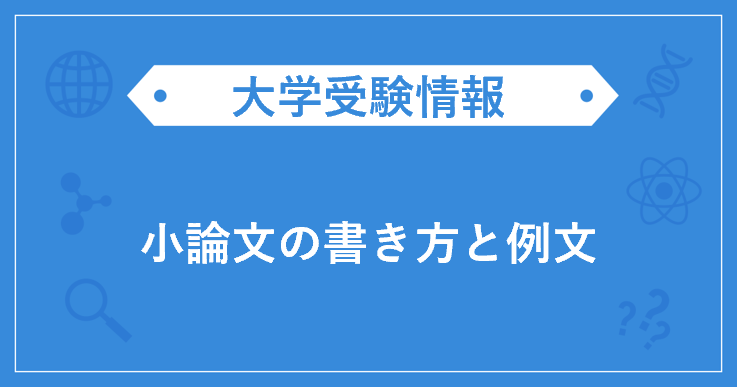
文部科学省が定める学習指導要領の中には、小論文という科目は含まれません。そのため、高校で十分な小論文の対策を行うのは難しく、大学受験の小論文を書けるようにするためには自己学習が必須となります。栄光では、小論文対策の授業も行っていますので、実例を交えながら、小論文で押さえたいポイントと具体的な対策方法をお伝えします。
目次
小論文とは
小論文とは、自分の主張を筋道立てて説明する文章のことです。論理的思考力や読解力だけではなく、国語力、教養、人間性などを総合的に測ることができるため、多くの大学の学校推薦・総合型選抜で採用されています。
ここに注意!作文や感想文とは違う
小学生のころからなじみのある作文や感想文と小論文は全く違うものです。
作文や感想文は自分の体験、そこから得た自分の気持ちや感想を書くものでした。そのため、構成についても細かな指定などはありませんし、表現についても書き手にゆだねられている部分が大きいです。
一方で小論文は、自分の意見を客観的に読み手に伝えるものです。作文とは異なり、論理的な構成が必要で、表現方法についても一定の決まりがあります。
文章を書くという点では同じですが、その目的が異なるので、内容や書き方も違います。違いを理解し、小論文の書き方を身につけていきましょう。
小論文の構成
小論文は「序論→本論→結論」の構成で考えるのが基本です。最初はこの三部構成で書けるように練習するのが良いでしょう。
序論で書くこと
序論ではテーマや課題に対する自分の意見を簡潔にまとめて書きます。
本論で書くこと
本論では序論で書いた自分の意見を支えるような理由・根拠を書きます。統計的なデータなどがある場合はこの段で入れるのが良いでしょう。
結論で書くこと
結論では序論・本論の内容を踏まえて自分の意見を再度書きます。最後まで意見が一貫しているかどうかをしっかり確認しましょう。
小論文の書き方
書く内容を構成に沿って整理しよう
書き始める前に、意見や根拠、アイデアを書き出したメモを作ります。どの内容をどの順序で入れるべきか、文字数に合いそうか、などをここでチェックしてください。
頭の中だけで整理すると、いざ書き始めてから内容を思い出したり、文字数を調整したりとロスが発生します。内容がまとまれば意外と書くこと自体に時間はかからないものです。
設問に沿った意見を書こう
小論文には、必ず設問があります。この内容を的確に理解し、設問に沿って意見を述べます。例えば「高校生がSNSを使用することの是非について」という設問の場合、使用することが「良い」か「良くない」か、自分の意見をまず書きます。
また、設問に条件がある場合はそれを外さないように注意しましょう。どんなに良い文章を書けていても、条件を満たせていなければ得点になりません。
意見に対する根拠を説明しよう
ただ意見を主張するだけでなく、例えば「SNSで多様な価値観の人々との交流ができるから」などの、意見の根拠を説明しましょう。その際には、客観的事実を挙げながら、自らの主張の重要性や問題点を説明するようにします。尚、根拠の説明は「同級生がみんな、利活用できているから」などの狭く偏った視点ではなく、立場の異なる人々からの対立意見も総合した論述を心がけましょう。
根拠の裏側にある要因を探ろう
SNSは世界中の人々と交流できるという利点がありますが、まれに社会問題を引き起こす場合もあります。賛否の根拠の裏側にある要因を探り、文章に盛り込んでみましょう。例えば、SNSの利用によって犯罪に巻き込まれる場合に、要因はSNS自体か、利用規則か、利用者か、などを掘り下げることで、賛否を超越した将来展望が発見できる可能性があります。
小論文で気を付けたいこと
小論文でしっかり得点するためには、細かなところまで気をつけて書ききることが大切です。以下は小論文を書くうえで、注意してほしいポイントです。練習のうちから意識するようにしてください。
文字数
小論文の多くの問題では文字数の制限があります。
○○文字以内:制限字数の9割が目安。制限字数をオーバーするのは×
○○文字程度:制限字数の前後1割が目安(600文字程度の場合は540文字~660文字)。オーバーしても問題ないが、1割以内に収める。
目安となる文字数に合わせて書けるように練習を重ねましょう。
原稿用紙の使い方
内容は完璧なのに、原稿用紙の使い方で減点されてしまうのはもったいないですよね。作文を書くときなどに習っていると思いますが、改めて見直しましょう。
| 注意点 | 正しい書き方 |
|---|---|
| 数字の書き方 | 横書き:漢数字もアラビア数字もOK 縦書き:漢数字のみ |
| 句読点・小文字・「」 | 1マス分使う |
| 句読点・小文字・」が行の頭に来る場合 | 直前行の最後の1マスにほかの文字とともに記入する |
| 最後のマス目 | 最後のマス目に句点を同居させると、字数オーバーになる可能性も。最終行は句点も1字と数える |
誤りやすい漢字・送りがな・かな表記
漢字、送りがな、かな表記の誤りに気を付けましょう。また、漢字で書けるものは原則漢字で表現します。しかし、思い出せない部分のみひらがなを使用した、漢字かな混じりの表現は適切ではありませんので、そうした場合は別の表現に置き換えるようにしましょう。
また、外来語の表記ミスにも気を付けましょう。
口語表現・略語
口語表現・略語の使用は原則NGです。
口語表現としてよくみられるものを、書き換えの表現と一緒にまとめていますので確認しておきましょう。
| NG表現 | 書き換え表現 |
|---|---|
| なので | このため |
| でも | しかし |
| ちゃんと | きちんと |
| ...じゃない | ...でない |
| お父さん | 父 |
| 僕 | 私 |
他にも、ら抜き言葉(見れる、食べれる、来れる)なども使用してはいけません。
表現技巧・無意味なカタカナ書き
体言止め、倒置法、省略などの表現技法は、その解釈を読み手にゆだねることになるため、書き手の意図を正確に伝えることを目的とする小論文での使用は避けたほうがいいでしょう。
また「思いやることがイチバンだ」などと無意味なカタカナ書きの使用も、同様の理由で控えましょう。
一貫した論理展開になっているか
小論文は意見を論理的に伝えるものだということは最初書いた通りです。誰かが読んだ時に、意見に筋が通っていると思ってもらえるような論理展開になっているかどうか、しっかり確かめましょう。
書き始める前のメモ段階でも論理を確認し、書き終えた後も落ち着いて最終チェックを行ってください。
小論文の例文
「テーマ提示型」の小論文の例です。
設問:「正義が抱える問題」について、あなたの考えを述べなさい。
第一段落【序論:意見】
そもそも正義とは、社会に所属する人々を公平に扱うための基準のことである。しかし、時折正義は対立し、それが問題となる。自分が主張する正義からすれば不正義なことであっても、それを正義ととらえる立場も存在するゆえに、正義を貫けば他者に不利益を与えることになるからである。
正義について正しく捉えたうえで、設問に対する意見を率直に述べることができています。また、理由説明とともに述べることで、スマートに相手に主張を伝えることができています。
第二段落【本論:根拠】
こうした対立の背景には、イデオロギーの存在がある。人々は社会生活の中でイデオロギーとともに正義を学び自らの内に形作っていくのであるから、外在するイデオロギーが異なれば形作られる正義も異なるものとなる。しかし、人々は自らのイデオロギーを帯びた正義を絶対視しがちゆえに、自らの正義を他者に押し付ける者や、他のイデオロギーを持つ人々の不利益を無視する者、その状況を改善しない者が生まれる恐れがある。こうして正義を掲げれば、同時に他方では不利益が生じることとなり、他者への悪影響が懸念される。
段落の冒頭でイデオロギーについて触れ、読み手にその対立の問題点をわかりやすく伝えようと工夫しています。
「正義が抱える問題点」にかかる理由が説明できています。それに加え、イデオロギーの対立が不利益を生むことを指摘しています。意見の根拠をしっかりと掘り下げていて、正義の問題性を述べることができています。
最終段落【結論:意見のまとめ】
たしかに、正義を択一的に見いだすのは困難だという指摘もある。しかし、思考を停止してはならない。イギリスの社会学者ギデンズが提唱した「第三の道」のように、イデオロギーを超えて、公正な正義を模索することは重要なのではないか。こうした思考を行うためには、自らの正義に対して常に疑問を持つとともに、他者が持つイデオロギーや正義を一度受けとめることが必要となる。ときには、集団内の利益をもたらすのであれば変更することも考えなければならないだろう。
最後に正義が抱える問題点をまとめつつ、今後はどういう展開をすべきか、論じることができています。このように将来の展望や改善策まで論じることができれば、真摯に課題に向き合っている姿勢を表現することができます。
小論文問題の種類
小論文問題は、主に以下の3種です。
- テーマ提示型
論述すべきテーマや設問のみが示され、それに沿って意見論述を行う。ヒントとなるような文章がないので、今まで学習してきた内容や体験などを思い出しながら根拠を考えていく必要がある。 - 課題文型
与えられた課題文を読み、それを踏まえた上で設問内容の記述を行う。筋道を立てて書くだけでなく、正しく課題文の内容を読み取る力が問われる。 - データ型
提示されている図表を読み取り、それに関する設問の論述を行う。データを正しく読み取り、その内容を意見論述に組み合わせる力が求められる。経済・看護などで頻出。
その他に、特定教科の知識を論述形式で述べさせるもの、英文での論述、課題文とデータが共に与えられ論述させるものなどもあります。
テーマ提示型が最も出題されますが、上位校を中心に課題文型もよく課されます。どのパターンが出題されても記述ができるよう対策を行いましょう。
【学部系統別】小論文で出題されるテーマと実例
小論文の出題のうち、どの学部においても共通して見られるテーマがあります。また、志望学部が学問対象として扱う社会現象・問題点・課題も頻出です。まずは、過去問を分析しましょう。志望校の過去の出題テーマに特徴や偏りがあるなど、傾向がはっきりする場合があります。
| 学部系統 | 出題テーマ例 | 出題実例 |
|---|---|---|
| 様々な学部・学科 | 環境問題 グローバル化 格差社会 AI 正義論 多様性 など | ・より円滑な異文化コミュニケーションを実現するために必要だと思うことを述べる。 ・自由と不自由の関係性について多面的に述べる。 |
| 人文科学系 | 日本人論 心の豊かさ 異文化理解 哲学 文学 倫理学 など | ・現代日本語の中で「漢語」を使いながら学問することをどう評価するか。 ・「タバコを規制するのであれば、アルコールも規制するべきではないか」という問題提起に対して他者危害原則などを踏まえた上で自らの考えを述べる。 |
| 社会科学系 | 少子高齢化 競争社会 マイノリティ ワークライフバランス など | ・日本社会における外国人に対する意識について述べた文を読み、日本人と外国人を差別化する視点について、自らの考えを述べる。 ・超高齢化を迎え、日本が社会を維持するにはどうすればよいのか。 |
| 教育・教員養成系 | 学力低下 いじめ 英語教育 発達障害 など | ・「学び合い」において教師はどのような役割を担うと考えるか。 ・部活動の指導を地域委託へ移行することについて自らの考えを述べる。 |
| 医歯薬系 看護・医療系 | 医療倫理 地域医療 生活習慣病 チーム医療 先端医療 など | ・資料を参考・引用し、SARS-CoV-2の初回感染時などについて今後調査、研究が必要と思われる点について意見と根拠を述べる。 ・医薬分業のメリットについて自分の考えを述べる。 |
| 体育学系 | スポーツ政策 障がい者スポーツ オリンピック ドーピング 子どもの体力低下 など | ・中学校や高校で制服を制定することに対して賛成か反対か自らの考えを述べる。 ・なぜ「運動好きな」子どもを育てることが必要なのか自らの考えを述べる。 |
| 自然科学系 | ICT技術 再生可能エネルギー ロボット 食料問題 生成AI など | ・スマートシティの実現に向けて必要となる科学技術と、今後の課題について述べる。 ・SDGsに対して、生命機能科学が貢献できる取り組みについて述べる。 |
小論文対策のポイント
過去問分析とネタ集め
小論文を書くにはテーマに関連した知識が必要とすることが多くあります。
小論文対策を効率的かつ効果的にするためには、過去問分析とテーマに沿った知識をつける対策(ネタ集め)が重要です。
自分が受験をする大学の過去問の分析は必ずしておきましょう。
過去の出題テーマに特徴や偏りがあるなど、傾向がはっきりする場合があります。
頻出テーマが分かったら、頻出テーマを扱った小論文の参考書や塾の講座を活用することで、小論文を書く時に必要な知識を身につけることができます。
書き終えたら必ず添削をしてもらう
小論文は特に自分で点数をつけるのが難しいので、必ず学校の先生や塾の先生に添削してもらいましょう。自分ではわからなかった誤字脱字や、原稿用紙の使い方のミスなども気づけます。
添削してもらった小論文はそのままにせず、添削内容を基に書き直しを行いましょう。課題を一つひとつ消化していくことで、文章力が向上していきます。
大学受験ナビオの小論文対策
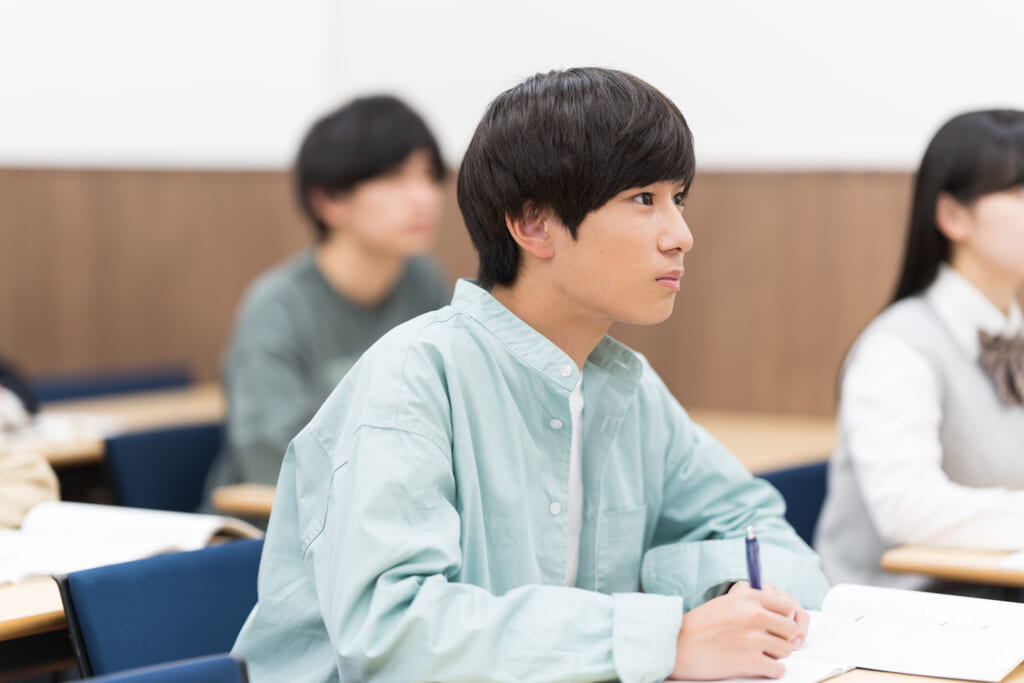
大学受験ナビオでは、小論文の原稿用紙の使い方から、気をつけたい表現や表記を踏まえたうえでの意見の述べ方、問題点の論じ方、文章の構成方法などを指導しています。小論文は自己採点が非常に難しく、自己学習だけでは力をつけにくいものです。
ナビオの小論文対策は、グループ指導、個別指導、映像指導から選べます。
グループ指導:講師や受講生と議論を通して構成力や論理的思考力を高める!添削指導付き!
個別指導:1対1もしくは1対2で、志望校や学部に合わせて添削指導!
映像指導:忙しい高校生活のスケジュールに合わせた視聴学習プランで、万全の対策を!
その他、小論文と志望理由書の書き方を学ぶ総合型選抜スタートゼミや直前期のZ会添削指導など、多くの指導形態から1人ひとりに最適な受験対策方法をご提案します。大学受験ナビオの小論文対策をぜひご活用ください。
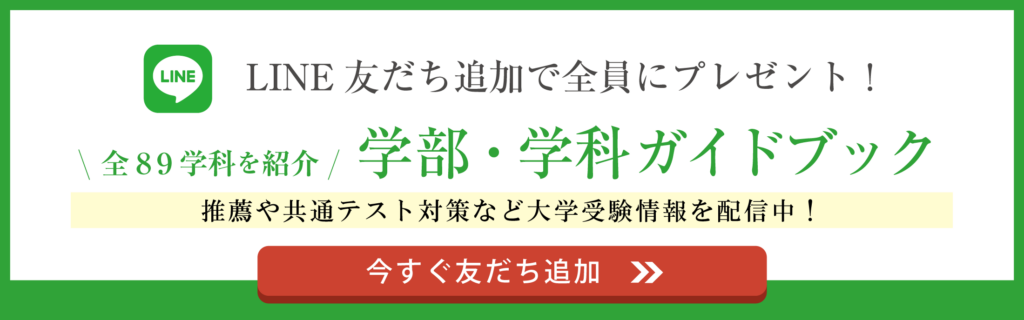









ご希望のコース・講座を
無料で体験できます













全教室の資料をメールで即お届け!
今すぐご検討いただけます