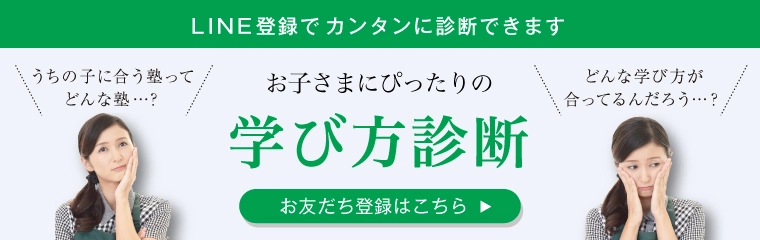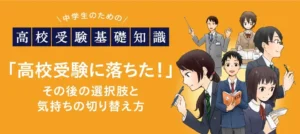高校受験を勝ち抜く。作文・小論文の書き方・コツを解説!
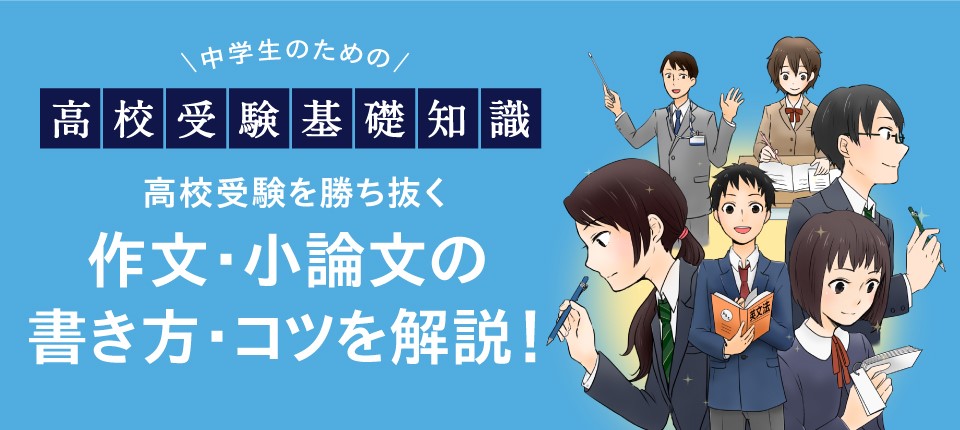

A高校の推薦入試は作文がありますね。対策はしていますか?
え!作文の対策って必要ですか?普通に書けばいいと思っていました。






高校入試の作文や小論文の試験は、書き方のコツをつかんできちんと練習すれば、点数が取れます。
得点源にもなるので、対策は必須ですよ!
でも、対策の仕方なんて、よくわからないです…。






そうですね…まずは、しっかりと書き方のルールを守る。
そのうえで、文章の型を身につけるトレーニングをしていきましょう!
目次
高校入試の作文・小論文とは?
高校の推薦入試では公立・私立を問わず、面接のほかに作文や小論文を課すのが一般的です。また一般入試でも、試験科目に作文や小論文を取り入れたり、国語の試験として出題したりする高校もあります。
作文は昔から何度も書いているからといって、対策をおろそかにする人がいます。しかし、近年の高校入試では、考えたことを自分の言葉で適切に表現する力を重要視する傾向があり、作文や小論文の結果が合否に大きく影響します。試験科目の中に作文や小論文がある人は念入りに作文対策も行いましょう。
作文と小論文は何が違う?
作文は、自分の体験や示された題材に対して、自分の心情や感想を書く文章です。小論文は特定の話題について自分の意見を述べる文章ですが、「そう考える理由」や「なぜそう考えるのか」といった理由や根拠までを説明する必要があります。小論文のほうがより論理性が求められますが、作文であっても読み手を納得させる説明は必須です。
作文・小論文を書くために必要な5つのポイントを理解しよう


高校入試の作文・小論文は、都道府県や学校によってテーマや文字数、形式が異なりますが、おもに、A.テーマ型(テーマに対して自分の意見を述べるもの)、B.資料読み取り型(文章やグラフ、図表などの資料を読み、それについての意見を述べるもの)という2つのパターンがあります。どんな出題にも対応できるように、まずは文章を書く際の基本となる5つのポイントを理解しておきましょう。
自分の考えを整理しよう
初めに、軸となる自分の考えや意見、伝えたい(主張したい)ことをはっきりさせましょう。作文では、自分が一番伝えたいことをひとつに絞っておくこと、小論文では提示されたテーマに対して賛成/反対のどちらの立場をとるのかを考えることが大切です。自分の意見が思いつかないときは、今までに自分が経験したこと、親や先生、友だちから聞いたことで、テーマに関連することはなかったかを、思い出すことから始めてみましょう。意見が固まったら、それはなぜかについてまずはまとめてみてください。主張と理由はセット、と覚えておくこと。
材料を集めよう
作文や小論文では具体例や体験のエピソードなど、意見のわかりやすく説明するための材料を用意することが大切です。箇条書きで構わないので、テーマや自分の意見から連想することを思いつくままに書き出してみると、読み手を説得する材料が見えてきます。
基本の型を活用しよう
読みやすい文章のためには、骨組みとなる全体の構成を決めることが大切です。文章は、「序論」「本論」「結論」の3つのパートに分けて構成するのが一般的で、それぞれのパートで何を書くのかを決めていくと、スムーズに書くことができます。書き方がわからないという人は、この基本となる型にあてはめて考えてみましょう。
序論
テーマに対する自分の意見や伝えたいことを簡潔に示す
本論
詳しい説明や、意見の根拠となる具体例・体験によって、序論で示した内容に説得力を持たせる
結論
本論をふまえて、意見や伝えたいことを改めてまとめる
制限字数内で書く
作文や小論文で「〇〇文字以内」とある場合は、指定された字数以内で書かなければなりません。オーバーしてしまうと、採点さえされないこともあるので注意してください。また少なすぎるのもNGです。制限字数の9割以上、最低でも8割以上でまとめるようにしましょう。「〇〇文字程度」とある場合は、前後1割以内(例:600程度→540~660字)が目安となります。
書き方や原稿用紙のルールを守る
作文や小論文の内容がよくても、原稿用紙の使い方や表現の形式を間違えると、減点されてしまいます。基本的なルールをしっかり覚えておきましょう。
- 文章の書き出しや改行したあとは、行頭を1文字分空ける。
- 句読点や促音、(二重)カギカッコは1マス使う。
- 行頭に句点や読点がくる場合は、前行の最後マスの下に書く。
- 縦書きの場合、数字は漢数字を使う。
- 省略表現や略語を使わない。
- 口語体(話し言葉)は使用しない。
- 文末は、「です、ます調」または「だ、である調」でそろえる
ひたすら練習を重ねよう
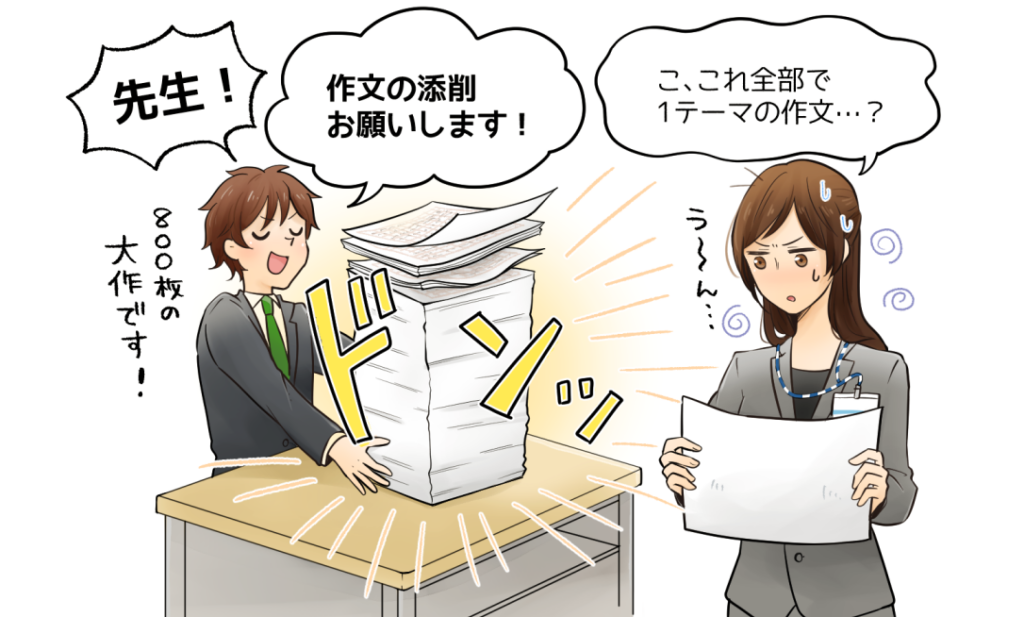
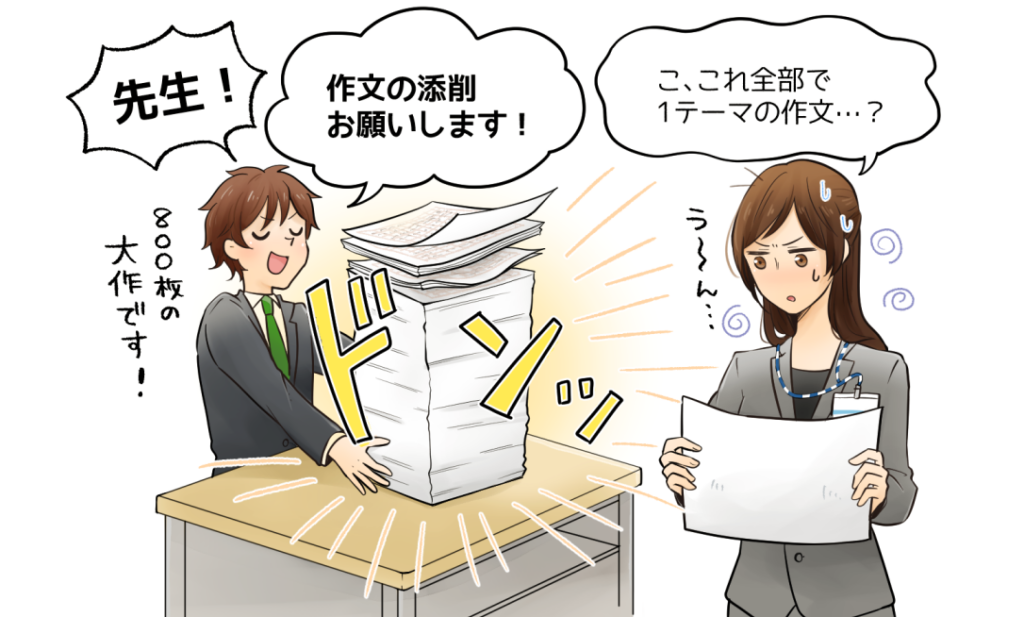
作文や小論文の基本的な書き方を身につけたら、どんどん練習するようにしましょう。何度も繰り返し書くことで、文章構成のコツがわかるようになります。また、志望校が決まっているのであれば、過去の入試で出題されたテーマ、字数や制限時間を確認してみましょう。入試本番と同じ条件・形式で書く練習をしておくことで、確実に実践力がアップします。
さまざまなテーマに挑戦しよう
過去の入試問題やたくさんの例題が掲載されている参考書を使って、さまざまなテーマの問題に挑戦してみましょう。回数を重ねていくうちに文章の組み立て方や書き方のコツがつかめ、対応力が身につきます。また、多くのテーマに触れておくことで、関連する知識や語彙を増やすことができるので、どんどん練習するようにしてください。
塾や学校の先生などに添削してもらおう
自分ではうまく書けたと思っても、相手に伝わらなければ意味がありません。自分ではどこが悪いのか判断がつきにくいので、書いた作文や小論文は、塾や学校の先生にチェックしてもらいましょう。添削してもらい、それをふまえて書き直すことが上達の近道です。
栄光ゼミナールなら、小論文・作文の上達につながる記述力が身につきます
学習指導要領の改訂や大学入試改革の方針を受けて、高校入試でも記述式問題が増加する傾向にあります。栄光ゼミナールでは、国語の授業を通して問題の意図を読み解く力や自分の考えをまとめ、伝える力も含めた「国語力」を強化。記述力を身につけて、作文・小論文問題でもしっかり得点できるように指導しています。
また、練習で書いた作文・小論文の添削も随時受け付けています。対策の仕方が分からない、文章を書くのが苦手という方は、ぜひ栄光ゼミナールにご相談ください。


栄光の高校受験対策では都道府県によって異なる高校入試の制度や出題傾向、最新の受験情報をもとに、進路指導を行ったうえで目標達成に必要な学習プランを作成し、苦手対策、定期テスト対策、志望校対策も、講師が生徒1人ひとりに寄り添って指導します。少人数で発言や質問がしやすく、仲間と切磋琢磨しながら成長できるグループ指導と、先生と隣り合わせでわからないところや苦手を中心に、自分のペースで学習を進められる個別指導があり、自分に合った指導形態で合格に向かって効率よく学習を進めることができます。家庭学習指導にも力を入れており、志望校合格に必要な学習内容をご提案。また、模試の結果を細かく分析し、苦手分野を徹底的に対策することで成績向上につなげます。











はじめての方はご希望の教科を
無料で体験できます
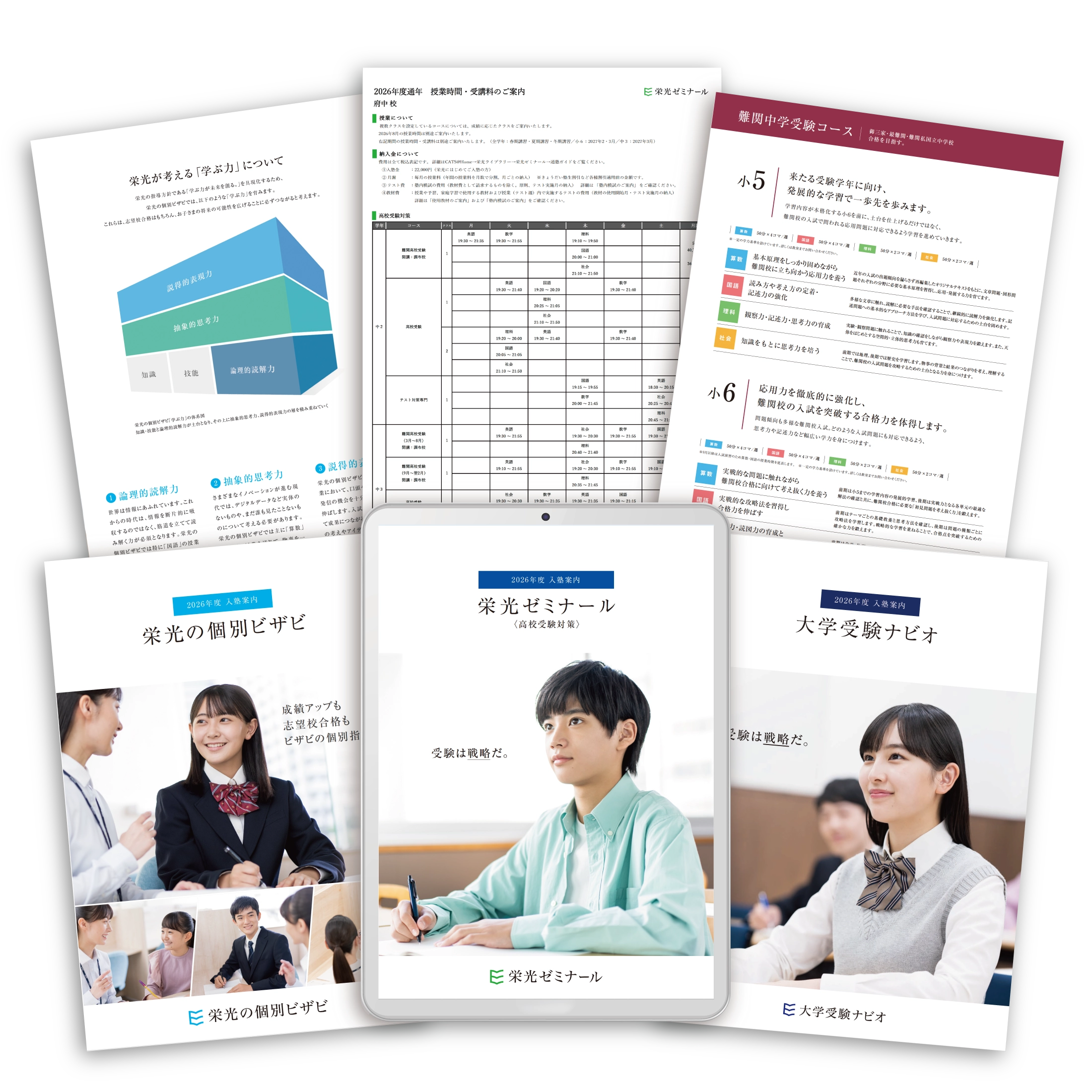
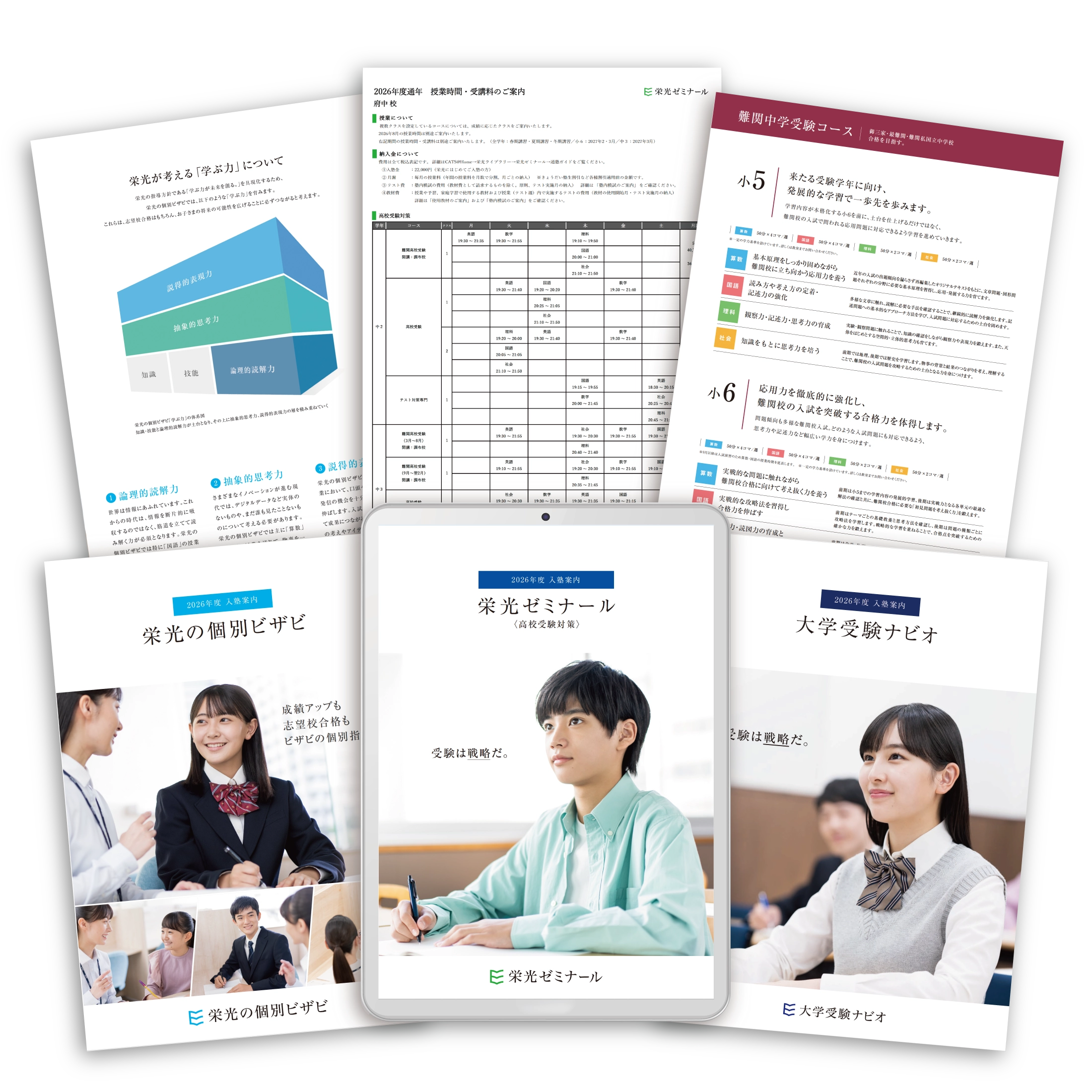









全教室の資料をメールで即お届け!
今すぐご検討いただけます。